こんにちは。あさぎです。
今回は「流浪の月」で本屋大賞を受賞した凪良 ゆう先生の「わたしの美しい庭」を読みました。
この作家さんはマイノリティや心の機微の描写がとても秀逸だと個人的に思っていてとても考えさせられる読書体験をもらえます。
わたしも「こうあるべき」という先入観に囚われてはいないだろうか?周りがこうだからこうしなければいけないと思い込んではいないだろうか?と普段の生活に忙殺されて思考停止している脳に喝をもらえます。
多様性を求められる世の中にはなってきているけども、自分の周囲とか小さい範囲ではやっぱりまだまだ「こうあるべき」という考え方はぬぐえなくて。自分の家族や大切な人がマイノリティな道に進んでも、真っ向から否定をするのではなくて寄り添ってあげられるような考え方を持ちたいと思ってます。
下記に当てはまるような方に読んでもらいたい作品です。
- 自分の生き方に息苦しさを感じる方
- マイノリティーな人々の考え方を覗いてみたい
- 世の中の「当たり前」「常識」に囚われすぎずに生きてる人の考えを参考にしたい
作品概要
あらすじ
小学生の百音と統理はふたり暮らし。朝になると同じマンションに住む路有が遊びにきて、三人でご飯を食べる。
百音と統理は血がつながっていない。その生活を“変わっている”という人もいるけれど、日々楽しく過ごしている。
三人が住むマンションの屋上。そこには小さな神社があり、統理が管理をしている。
地元の人からは『屋上神社』とか『縁切りさん』と気安く呼ばれていて、断ち物の神さまが祀られている。
悪癖、気鬱となる悪いご縁、すべてを断ち切ってくれるといい、“いろんなもの”が心に絡んでしまった人がやってくるが――
ポプラ社HPより引用
感想
「流浪の月」に続きこの作品も「普通」「普通の人の常識」とは?と考えさせられる。自分も20代で一般でいう普通の人のレールを大きく逸れてしまい共感する部分が多々。
マンションの屋上の縁切り神社を通して紡がれる人間関係。
高校時代に恋人を交通事故で亡くして、それでもずっと想い続けているアラフォーの桃子。「結婚=幸せ」の図式が私には理解が難しい。確かに老後を思うと一人よりは二人でと思うのも分からないではないけれど。結婚というものは周りに言われてするものではないよね。と、どうしても思ってしまう自分がいて。一人の人を20年近く思い続けるという芯の強さがとても素敵。それを貫き通す難しさは読者の想像以上だろう。
恋人が世間体を気にして異性と結婚すると言い出し、振られたゲイの路有。ここでも世間体…。親に泣かれたらそうなってしまうのだろうか。世間体のために結婚した相手にも振った路有にも失礼なのではないのだろうかとか思ってしまうのだけれど。周りを気にせずに自分を貫き通す難しさは想像に難くない。なかなかに酷い描写の路有の元彼。でもこれがLGBTの現実だったりもするのだろうか。
仕事に忙殺され、いつの間にか心に負荷がかかってしまいドロップアウトした基。自分の場合は仕事だけではないけれど、うつの話が自分に被りすぎてて読んでいて当時を思い出してしまい辛かった。病気なのだから自分も、自分を心配してくれる周りも悪くはない。なのだけれど「理解」にまでは至らなかったなぁ、と。だから「自分の理解が至らないのなら通り過ぎればいい」という統理の言葉がとてもしっくりきた。
自分の暮らしている環境からか、常識に囚われることのない百音の存在に救われる。
ここに出てくる登場人物の皆が「こうあるべきだ」とい世間の常識、先入観と闘いながら前へ向かって進んでいる。私も周りに流されすぎないように、自分がやりたいことを優先して生きていきたい。自分を幸せにしてあげられるのは自分なのだから。



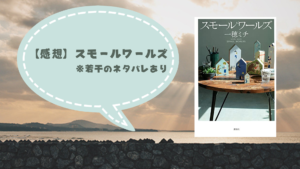
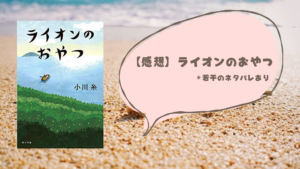
コメント